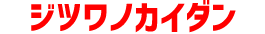自分の部屋に閉じ込められた話です。夜中にトイレに行きたくなり、目を覚ましました。しかし、真っ暗な中で、部屋中を触れて回っても、扉のドアノブが見つけられません。部屋から出れなくなりましたが、一度布団に戻り、改めて起きたら、そこにはドアノブがありました。
あれは秋の夜の事であったでしょうか
10代の頃の話です。夕食や入浴を終え、自室で本を読んでいました。気が付くと0時をとっくに過ぎていて、いい加減に眠ろうと思い、部屋の電気を消しました。
その日は雨風が強く、雨戸をきっちりと閉めていました。寝るときに、豆電球を点ける習慣がなかったので、部屋の中は真っ暗でした。
布団に入ったものの、目が冴えてしまい、なかなか眠りにつけませんでした。ようやく意識が薄らいできたとき、なんだか急にトイレに行きたくなりました。
でも、やっと眠くなり始めたのに、布団から出るのも億劫だったので、朝まで我慢することにしました。
しかし、やはり我慢ができず、結局布団から出ることにしたのです。起き上がって、振り向き、数歩踏み出せば、部屋の扉があります。
たとえ暗くても、慣れた自分の部屋です。いつも通り、扉に手を伸ばしました。ところが、あるはずのドアノブがないのです。
両手を使って、手の届く範囲で部屋の扉を触りました。くまなく触っても、やはり感じることはできません。
「寝ぼけているに違いない」
そう考えて冷静になろうと部屋の隅々まで触れながら歩きました
扉の左横にはピアノがあって、ピアノをつたって行けば、雨戸で閉ざされた窓があって、そしてベランダへ続く窓も触って感じることができます。
クローゼットにも触れ、一周して扉の前に戻り、改めて手を伸ばしました。それでも、やはりドアノブがないのです。
そう、つまり自分の部屋に閉じ込められたのです。
「そんなはずはない、落ち着け」と自分に言い聞かせようとしても、胸の鼓動は早まるばかりです。試しに電気を点ければよかったのです。
けれども、本当にドアノブがないことを確認してしまったら、部屋から出られないことを視覚的にも理解せざるをえなくなってしまうのです。その恐怖が勝り、なかなか点けることができませんでした。
何か妙な気配を感じるわけでもないのに、とてつもなく怖くなってしまい、思わず布団にもぐってしまいました。「朝になれば、家族が助けてくれる」そう信じて、うずくまっていました。
ただ、トイレに行きたいという感覚は消えず、意を決して布団から出て、恐る恐るドアノブへ手を伸ばしました。
すると、今度はあっさりとドアノブを掴むことができました。用を足し、部屋に戻るとようやく落ち着くことができました。そして、その反動なのか、今度はすぐに眠りにつくことができました。
翌朝目が覚まして、振り返っても、とても夢とは思えませんでした。扉の木目も、ピアノにかかっているレースのカバーの感触も、窓ガラスのざらつきも、すべて実感があったのです。
今でも時々そのときのことを思いますが、あまり考えすぎると、また閉じ込められてしまうような気がしてしまい、なるべく思い出したくない記憶の一つとなっています。